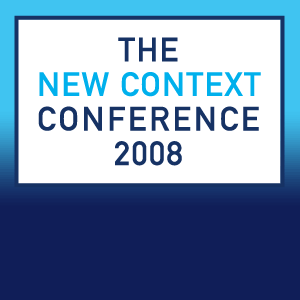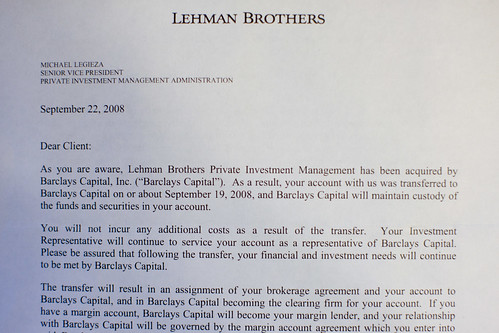From Fumi Yamazaki:
LinkedIn と
Joi
Labs と
慶應義塾大学國領研究室の合同プロジェクトとして行っている、
"
Business Success in Open
Networks" の第3弾映像を公開しました。
Episode1では伊藤穰一(Joi)氏/國領二郎氏により、「日本におけるオープンビジネス」の形と可能性やその背景にある考え方(サクセスとは何か/オープンビジネ
ス、オープンネットワークとは何をもってオープンと呼ぶのか/米国は本当にオープンなのか等)について考察が行いました。
Episode2では、Joiと國領先生をホストに、新生銀行の八城政基様に日本のビジネスの閉鎖性やエクソン社での人材育成方法についてお話を伺いました。
Episode3
では、Joiと國領先生をホストに、マネックスの松本大さんにお話を伺いました。松本さん、貴重なお話をありがとうございました!
早速映像をご覧ください。
<今の日本について:問題はヒエラルキー>
(松本)今の日本企業の問題は、ヒエラルキーが上がらないと力を持てないこと。「上から下に」譲るのであって、「下克上」はない。下の人は上に行くまでは発言しない(発言力がない)が、上に行ったときには価値観がおかしくなっている。
<「パラダイス鎖国」な日本>
(國領)「パラダイス鎖国」という書籍があるが、このタイトルに象徴されるように日本は変にcozy(居心地がよい)でパラダイスなことが問題。
(松本)日本では、外からは発言が届かない。中にいると発言が許されない。だから、エッジ(へり)で努力している。「最大の旧体制は自分の中にある」と自分に言い聞かせている。
<エッジをきかせるために気をつけていることは?>
(松本)人も会社も必ず古くなっていっており、死に向かっているものだ。だから、常に新しい物を入れないといけない。
(Joi)大企業をやめてベンチャーに来ても、頭の中だけがベンチャー/エッジ/シリコンバレー/アヴァンギャルドな人がいる。人は簡単には変わらない。
<マネックス社のロードマップを作ってわかったこと>
(松本)マネックスの10年プランのロードマップを作った。
まずトップダウンでフレームワーク(価値観/10年後のビジョン)を作って全社員に説明し、それを模造紙に貼った。テクノロジー/サービス/人事等についてのマイルストーンが書かれている。そのマイルストーンの間を社員がポストイットでどんどん埋めていく。
マネックスの社員は160人だが、400枚ものポストイットが貼られた。そのうち、4割程度を残して作り直して、社員全員にフィードバックした。
トップダウンで出したフレームワークは、ストレッチな物だった。それに対して経営層は「無理がある/社員がついてこないのでは?」という反応だった。しかし、逆に若者達は「面白い!できる!やろうぜ」という反応だった。それが逆流して、上の人達もノッてきた。
上の人達も元々はフォワード型の人のはずが、立場等でブレーキ体質になって
しまう。バランスを崩そうとするCEOに対して「それは駄目です!」と言
い続けた結果、ブレーキ体質になってしまう。ところが下からくると、ノってくることがわかった。
<日本社会は世界で最もクローズド?>
(Joi)日本人は今後変わっていくだろうか?
こういう仮説がある。アメリカはオープンネットワークなので誰でも入れるし誰でも出て行けるため、「信頼に足る人物かどうか」の
チェック機能が働く。いい人は残して悪い人は排除する、循環があるネットワーキング。例えば外資系企業だと、会社の名前よりも「個人の信用度」が重要視される。
日本はクローズドネットワークなので逃げることができず、罰することができるため、信頼は必要ない。社員を会社の中にロックインして逃げられないようにすれば、個人の信頼は必要なくなる。そういう仮説。
マネックスは日本型?アメリカ型?
(松本)マネックスの企業文化は日本型ではない。ただし、日本という国の閉鎖性は非常に強く、一人一人の個人の中にその閉鎖性は存在している。
日本は世界で最もクローズドなネットワーク、クローズドなコミュニティ。双方向の意味でホモジニアス。世界中で日本人はほぼ日本にしかおらず、日本の中にほぼ日本人しかいない。
ただし、国全体が少しずつ変わってきていると思う。
<「お上」依存が薄れ、変わりつつある日本>
(松本)日本はオーソリティに対する考え方が強いが、近年「お上」に対する信任が落ちてきている。例えば保険料を若者が払わず、「どうせ年金はつぶれる」と考えている。会社に対する考え方もかわってきている。かつては金融機関はつぶれないと考えられていたが、長銀、山一がつぶれた。オーソリティに対する依存度が薄れてきており、オープンネットワークにアシュアランスを探さざるをえなくなるだろう。
<人材は供給が需要を作る>
(國領)戦時中の巨大産業(中島飛行機等)が戦後解体され、基礎的技術力はもっているが自由になった人たちが、浜松等でネットワーキングをしてホンダ等を作ってきた。金融業界は山一、長銀等のOBがスオピンオフして面白いことをやっている。
(松本)人材は供給が需要を作る。シリコンバレーも東部の金融でボコボコになった、ファイナンスの知識がある人たちが起業していった。
(Joi)当時と今との違いは、当時はパラダイスと勘違いできない程焼け野原だったことと若い人が残っていたこと。今はパラダイスと思っている人がいる/高齢化の2点が問題。
<5年後、日本は変わる>
(松本)日本が変わらない理由は戦後の成功体験。官僚/政治家/プライベートセクターみんな、第二次世界大戦後、焼土と化したところから世界一位へ成長した体験を持っているため、ちょっと悪くなってもあれだけできたので大丈夫だと思っている。
そのような人は5年後にはいなくなっている。終戦時10歳の人は5年後には80歳になる。CEOのジェネレーションチェンジが起こり、政界/官僚も変わる。成功体験者がプレイヤー層にいなくなる。
先日若い社員と話していたら、「僕は産まれてから一度も日本がすごい国だと思ったことがありません。」という。そのように思っている、成功体験に縛られていない子達は、普通に競争するだろうし、オープンネットワークでないと勝てないなら普通に取り入れるだろう。
<ベンチャーではなく研究所に流れる日本の技術関連資金>
(Joi)技術者に流れるお金は、電話会社経由で研究所に流れるお金が多い。インターネットの世界では、例えばGoogleはAdSense等のインターネット広告によって、5000億以上のお金をベンチャーの原資にした。日本でモバイルEコマース等の1000億規模の資金は研究所に一旦入った物を吸収する形になり、イノベーションやベンチャーにつながらない。ネットがモバイルに行くとベンチャーに流れるお金が減るのではないかと懸念している。
<次の世代へ>
(松本)アメリカだと、上司は「お前がやれ」、国際会議も「お前が行け」という。日本だと、国際会議は同じ人が行く。「次の代に任せよう」、「任せて自分も恩恵を受けよう」という発想ではなく、全部自分で刈り取ろうとする。
日本は老人が楽しい社会にするべき。今は、上に長く残らないといい思いができず、下が迷惑を受ける社会。
子供や孫もパッケージにした考え方を提示すべき。「あなたがこうすると、子供/孫はこうなっちゃいますよ」と。
<人材は「人づて」で探す>
(國領)人の流れはどうすればよくなると思うか?仮説としては個人レベルの信頼のネットワークがポイントなのではないかと考えている。
(松本)人の探し方は、結局人づて。リスクを落とす最大の方法は推薦/レファレンス。「自分にとっての目利き」(この人の推薦なら信用する)はいる。自分が人を紹介してもらう時も誰に紹介してもらうかが重要だし、自分が会う人も誰に頼まれたかで会う人を決める。
<松本氏の夢の組織論>
(松本)夢の組織は、「若くても偉くなる」というだけではなく、「年をとった人が同じ組織の中でポジションが下がる」組織。
経験/知識がある人がいるのに、年をとったら止まっているかやめるかしかないのはもったいない。35〜40歳過ぎたらポジションが下がってくる人が多くなると、心理的抵抗がなくなるのでは。
家族では、親が子供に「お前の代だから」と譲り、親父は手伝いをすることもある。これを企業でもできると、人材活用方法としてはローリスク、ローコスト、ハイリターンなのでは?アメリカ的能力主義とは異なる能力主義が作れるのではないか。
![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)