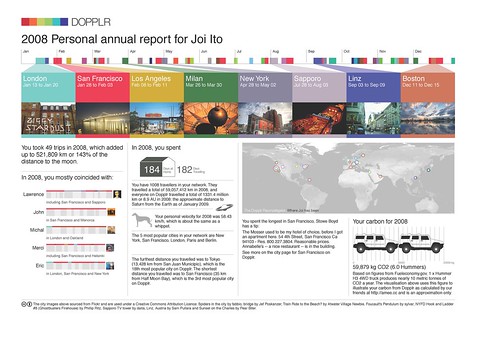ルールは以下の通り。
1.この話を振ってきた人物にリンクし、投稿内にこのルールを記載すること。
2.自分に関する事実を7つ、投稿内で述べること。
3.投稿の最後に、あなたがこの話しを振る7人の人物の名前を記載し、そのブログへのリンクを張ること。
4.話を振ったことを本人に伝えること。
僕の振り元はMitchell Bakerだった。
1.僕が憶えている最も古い記憶は、釣り用のリールに砂を入れてしまって父親に怒られている光景だ。我々の家族はとても貧しかったにもかかわらず、うちの両親が古いポンコツ車でアメリカを横断するという名案を思いついたらしい。道中のある地点で、食べ物を買うか釣りざおを買うかの判断を迫られたようで、うちの父親、釣りざおを買って夕食の魚を釣り上げることに決めたそうな。ところが僕が釣りざおのリールに砂を入れて壊してしまい、全員夕食を抜くハメに。少なくとも僕はそう聞かされている。いずれにせよ、父親のあまりもの激怒っぷりに、怒られた事実が僕の少年時代の記憶に深く刻まれているようだ。3歳くらいのことだったと思う。
2.僕の初めての仕事は米国ミシガン州サウスフィールドにある「ウェット・ペット」という熱帯魚屋さんだった。そこに100個ほどある水槽に入っている魚のラテン語名は全て知っていたし、生まれて初めて本格的にハマったのが熱帯魚だった。12歳くらいだったと思う。タンディ社のマイコン「TRS-80」が発売されたのも確かこの年だった。僕は爬虫類・虫系・両生類にも凝っていて、時計付きラジオの中身をくり抜いてペット用のタランチュラを日本に密輸入したこともある。
3.僕が初めて本物のバーでまともな酒を飲んだのは15歳頃のことだった。母親の友人である日本人のビジネスマンが飲みに連れていってくれて、その日本人のガールフレンドであるフィリピン人として皆に紹介された。
4.僕は高校時代、「エントロピー」と銘打ったアングラ新聞の共同創設者にして共同編集者だった。最近読み返してみると、我々は公式のほうの学校新聞を批判したり、文法などの規則の不要ぶりを訴えたりするのに随分と時間を浪費していたことに気付くよ。放課後に校舎内に侵入して謄写版印刷機で紙面を印刷したのを記憶している。当時の共同編集者であり、バックナンバーを発掘してくれたEiji Hirai氏に感謝したい。Eijiによると我々は当時、新聞の編集にWordStarを使っていて、文字を太字で印刷する方法を解明して大得意になっていたそうだ。1982~84年頃のことだ。
5.僕はシャイで、けっこう怠け者だ。知らない人と出合うことの恐怖や、だらけグセの克服するために人生の大半を費やしてきた。やることリストの一番下に一番やりたくないことが溜まり、それらは決してこなされることがないのに気づいた瞬間を今でもおぼえている。そこで僕は、やることリストの上ではなく、一番下から取りかかるようにした。自分の問題を克服するために、こうした細かい工夫をするように自分を仕向けていったわけだ。結果として、僕は怠け者ではあるが、訓練によって修正が可能なことがわかり、若者時代よりも少しだけ生産的な活動ができるよう、自己訓練ができたようだ。
6.僕は昔から歌手になりたかった。けれど歌は苦手だ。母親は歌が上手く、遠い親せきを含めればプロのミュージシャンが大勢いる。中学の合唱団選抜試験は不合格だったし、カラオケではいつも恥をかく。そして歌が苦手な自分が嫌いだ。父親も歌えないので、彼のせいにしておこう。
7.僕は高校時代、レスリングの1984年度極東トーナメント(確か極東地域の米軍系高校、インターナショナルスクール計27校が参加)の自分の階級で準優勝したことがある。優勝の栄冠は米空軍の横田基地のMike Rothstein君に奪われてしまった。スポーツ面ではそれ以後、衰退の一途をたどっている。
以下の皆さんにこの話を振ります。
Sean Bonner、Mimi Ito、Lawrence Lessig、CatspawことMichelle Levesque、Loic Le Meur、Ethan Zukerman、そしてThomas Crampton。
![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)