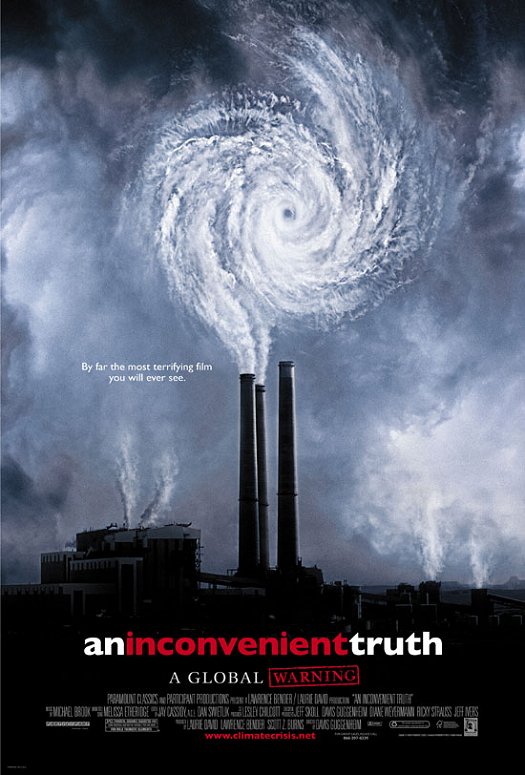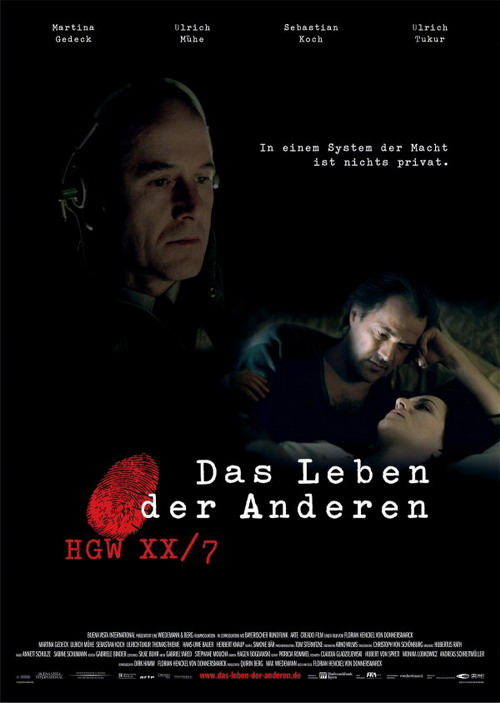昨日僕と村上龍さんとの対談本「個」を見つめるダイアローグが出ました。
Amazon.co.jp売ってます。
朝日新聞レビュー
Epilogue
日本生まれで、アメリカで育ち。その後の人生も、二つの国を行き来しながらすごしているわたしには、それぞれの国を「外側」から見る習性がいつのまにかついたような気がします。アメリカはよく「巨大な民族の坩堝」といわれますが、わたしからすると、たしかに民族の坩堝ではあっても、けっして文化の癒合した国には見えない。一方、日本という国は、よく「均一国家」ととらえられがちですが、わたしのイメージは、シルクロードの東端に位置する、多様な文化の融合した国、それが日本です。
豊かで、懐の深い、多様な文化をもつ日本ですが、しかしその多様さゆえに、「複雑な国」として映るのもたしかです。わたしが複雑な思いにかられるのは、日本人自身が自らの国の多様な文化のよさに気づいていないのではないか、という点です。
一つは歴史的な背景があるでしょう。太平洋戦争での敗戦以来、日本は非常に奇妙な状況に置かれてきました。反共をかかげるアメリカの戦後政策のなかで、日本は東アジアの盾として、厚く保護されてきました。その間、日本人は独自の勤勉さと意欲で、他国が脅威を感じるほどまでに経済を成長させてきました。しかし、経済的な豊かさを背景にした優越感をもつ一方で、自立した精神性をもてず、歪んだままの劣等感を内在させてきた日本人も多くいたのではないでしょうか。それが英語でコミュニケーションがとれないことと相まって、国際社会との非常に奇妙な関係を生み出した――。わたしには、そんなふうに思えます。
それと、バブル崩壊の問題。これも日本人にとって大きな痛手でした。高齢化社会への対応が急がれる中で、日本人は「失われた10年」をさまよい続けました。小泉首相をはじめとする改革主義者たちは、行財政改革を御旗に改革を推し進め、いま回復の兆しがほのかに見えてきているかのようにいわれます。しかし、この景気回復は主に中国の急激な経済成長に支えられたもので、それによって潤ったのは、建設や機械、原材料といった旧来型の産業構造の中の企業群です。にもかかわらず、多くの日本人は「復活のきざしが見えてきた」と安堵の息をついています。
しかし、ここでわたしがまた心配するのは、日本という国を「外側」から見据えるチャンスを日本人は失いかねない、ということです。バブル崩壊はある意味で、そのチャンスでした。経済だけに頼らぬ、多様な文化をもつ国のあり方について、あるいは経済的な豊かさに頼らぬ「個」のあり方について、みんなで対話を重ねるチャンスでもあったのです。そのチャンスが、見せかけの景気回復の兆しが見えてきたことで、また遠くにかすんでいくのではないか。そして、日本人はまた、心地よい「内側」の世界に安住することになりはしないか。わたしには、それが心配なのです。
ちょっと視点を「外側」に置けば、日本の文化は世界の人から注目を集めていることはよくわかります。日本の製品やブランドには相変わらず高い評価があるし、坂本龍一さんのように、世界各国で厚い支持を集めている日本人アーティストもたくさんいます。しかしその一方で、「内側」にこもりつづける日本人が相変わらず多いのもたしかです。
一つは、先にも述べたコミュニケーション力の問題があるでしょう。そしてもう一つ、あえて言うとすれば、自ら考え、ときには権力に異を唱える覚悟。それが、いまの日本人には欠けてしまっているような気がしてならないのです。自らの視座をもって「外側」の人間とも対話を重ねることは、自立した国をめざすうえでも、自立した「個」を確立していくうえでも、欠かせないことはいうまでもありません。
世界的な視点で物事を考える習慣を多くの日本人がもたないまま、一方では日本の文化や製品は高い評価を受けている。このゆがんだ構造を修正していくことが、これからの日本にとっては、とても重要なのではないかと思います。
そんな日本という国へのさまざまな心配事を胸に抱えながら、忌憚なく、そしてフランクに、村上龍さんと対話を重ねたのが本書です。わたしは、むかしから村上龍さんの大ファンでしたが、坂本龍一さんに紹介されたのがきっかけで、以来、親しくおつき合いさせていただいています。龍さんは、日本にいながら、日本という国を「外側」から見据えることのできる数少ない作家の一人だと、わたしは思っています。そして、誰よりも、世界における日本の状況を理解し、日本の将来の姿を見つめてきた作家ではないでしょうか。
そんな龍さんと、日本という国を改めて「外側」から見つめることができたのは、わたしにとってとても貴重な体験でした。なによりも、対話を心から楽しむことができました。
こんなフランクな対話が日本のあちこちではじまることを、わたしは願っています。「忘れられた小さな島国」になる前に、もっともっと対話を積み重ねてほしい。それが、本当の幸せの形を見つめなおすことでもあると思うのです。
![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)