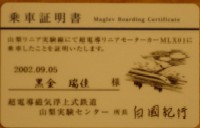Firefox はカラープロファイルに対応しているけれど、設定を手動で有効にしなければならない。
やり方を詳細に解説した素晴らしいブログ記事がいくつかあるので、詳しくはそちらを読んでもらうとして、この機能を使うことで色の正確さが大幅に向上するんだ。
カラープロファイルは、画像内の色がどのように見えるべきかをコンピュータに指示する地図のような役割を果たしてくれる。カメラ、モニター、プリンターにはいずれもカラープロファイルが設定されている。画像のカラープロファイルは、画像の色をプリンターやモニターのプロファイルにマッピングすることで、画像の色の正確なレンダリングを可能にする。
以前のFirefox(および、7以前のInternet Explorer)は画像のカラープロファイルを無視して、OSに対して、プロファイルが基本的なカラープロファイル(sRGB)であると伝えていた。大まかな話としては、大半の画像ファイルはsRGBなので問題ないはずだ。しかしこのことにより、しばしばインターネットに投稿した写真の見え方が画像エディタ内のそれと変わってしまう(色あせて、彩度が落ちてしまう)ため、iPhoto、Aperture、Lightroomなどで彩度やカラー・バランスを微調整する人にとっては、とても大きなフラストレーションを生む原因となっていたんだ。「sRBGとしてセーブ」を使うことでこれらの問題をある程度は回避できたものの、それでも問題が起こることが多かった。(僕がFlickrに投稿した写真の一枚に関する会話で、色関連のマニアの方々数名が解説してくれた。)
色の深遠なる機微に関する話題が興味深いのは確かだけれど、大半の人々にとっては「Firefox 3でカラープロファイル対応を「有効(on)」にすれば、多くの画像が元の色に格段に近い状態で表示され、色あせの度合いが弱まる」ということだ。やり方はこうだ。Firefox 3のアドレスバーに「about:config」と入力して、確認ページを進んでいく。「find: gfx.color_management.enabled」で設定項目を見つけたら、有効(true)と表示されるまでダブルクリックする。最後にFirefox 3を再起動すればいい。
Eye One Matchなど、モニターの色を調整するためのガジェットやソフトウェアのパッケージを使えばモニター(およびカメラやプリンター)の色調整ができる。万人が実際にその手間暇をかければ、皆同じ色を目にすることになるはずだ。問題は、未調整のモニターの多くで(たとえ同じシリーズのモニターであっても)色の映り方が違ってしまうことなんだ。これはつまり、未調整のモニターを使っている場合、写真の作者が色の「ずれた」画像を作ってしまい、それが別の未調整のモニターで表示された時にさらに「ずれて」しまうということを意味する。以前はブラウザ側でさらに「ずれ」が加わっていたわけだけど、カラープロファイル対応により正確な発色に一歩近づいたことになる。全部やろうと思う人はモニターの色調整が必要になるわけだ。
MozillaはどうしてSafariのようにデフォルトでカラープロファイルに対応するようにしていないのだろうか。(IE 7でもデフォルトでは無効になっている。)10~15%ほどパフォーマンスに悪影響が出るということはあるらしい。でも僕も手元で有効にして使っているけれど、体感できる違いはないように思える。いずれにせよ、最適化したうえで将来的にデフォルトで有効にする動きはあるそうだ。でも現時点では、保証を破棄してFirefoxをハッキングするしかないということだね。
![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)