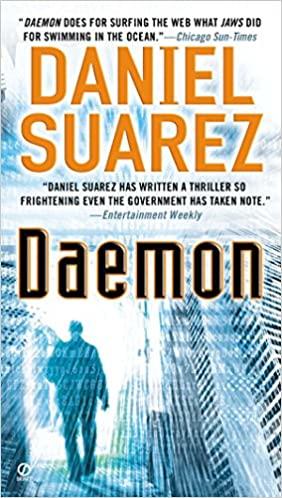この前の週末、Preventive Medicine Research Institute(PMRI)が開いている静養プログラムに参加した。PMRIは、Dean Ornish氏が、予防医学に関する自分の研究を進めるために設立した組織だ。
このブログの読者ならご存知のように、僕は2006年12月に完全菜食主義の食生活を始め、運動と瞑想をするようになり、今では「Joi 2.0」にバージョンアップするに至っている。それ以来、僕の頭と体の中で起こっていることをこのブログの読者や友人たちに伝えようとしてきた。
その間に、TEDカンファレンスでDeanの講演を聴く機会があった。そこでは低脂肪な完全菜食の生活によって、心臓病の進行を遅らせることができるばかりか、その病状を改善できることが話されていた。そしてそのとき彼の名前は、僕の頭の中で、「クールな要チェック人物」の一人としてファイリングされた。
Lawrence Lessigは前回のTEDカンファレンスでDeanと出会い、その際に再会を約束していた。最近体調が戻りつつあるLarryは、僕が興味を示すことがわかっていて、一緒にDeanに会いに行かないかと誘ってくれた。そしてDeanに会った後、我々は近く開催される静養ウィークエンドに招待され、彼の新著「Spectrum」ももらった。
Larryはあいにく参加できなかったのだが、僕はどうにかスケジュールを合わせることで、参加することができた。
Deanの本を読み、静養ウィークエンドに参加して、僕は彼のプログラムが幸福と健康を増進するのに非常に効果的なものだという結論を下した。そのプログラムは、僕がそれまで取り組んできたすべての要素を一所にまとめてそれを確たる理論で結びつけた内容だった。このプログラムの様々な要素の効果を証明しようとする、彼のその研究への探求心と情熱が、このプログラムを他の代替医療系、ライフスタイル系のプログラムとはまったく異なるものにしている。彼は流行としてのウェルネスに最高水準の科学的基盤をもたらす人物であり、そういったことが、この手のものが本流として定着するのに不可欠な要素なのだと僕は思う。
Deanのプログラムはただのダイエットではなく、食生活・運動・リラクゼーション・親交という4つの重要な要素を含んでいる。静養ウィークエンドで、我々は終始、素晴らしく健康的な食事をとり、ヨガとエクササイズ、瞑想に取り組んだ。医学と科学についてのディスカッションもした。個人個人が抱える課題についてとてもオープンかつ親密な雰囲気で話し合う、少人数のセッションも行なった。これらは僕が想像していたよりも遥かに効果的なものだった。
このグループセッション、心理療法やグループセラピーのようなものではなくて、少人数で互いに気持ちを分かちあう場だった。参加者は開始後すぐに親密になり、そのセッションは慈愛が湧き出すかのような場になっていった。僕がそれまでに取り組んでいた「健康の方程式」には、この「親交」という重要な要素が欠けていたのだ。Deanの研究とこれらのセッションは、僕にその重要性を確信させ、慈愛のような精神的な部分での僕の目標を完成させてくれた。
Deanは、親交・リラクゼーション・食生活・運動のいずれもが我々の健康に影響していることを研究している。特に動脈の閉塞や炎症全般が、これらの要素の影響を受けやすいそうだ。彼は、動脈の閉塞と炎症が、癌、糖尿病、心臓病、高血圧、そしてEDでさえもその原因になっているとする。
こういったことはほとんど彼の本の中で解説されている。この本でひとつ面白い切り口だなと思ったのは、食べ物というものはきわめて不健康な部類のものからきわめて健康的なものまで、あたかもスペクトルのように分布しているとしたところだ。最も健康的な食生活(例えば僕が去年やった完全菜食主義のスーパーダイエット)を選択すれば、心臓病の病状さえ改善できる。すでに十分に健康的かつ幸せなのであれば、すこし緩めの感じでもいい。Deanは、自分が何を食べたかについて決して罪悪感を抱くべきではないが食べたものがどれだけ健康的なのかは認識しておく必要がある、と提案する。彼は様々な食べ物についてその健康度を評定した表を作ったりもしている。自分に合った健康度の食生活を選択し、それに適度に調節を加え、時には好きなだけ食べればよい。彼はダイエットに罪悪感が伴うことを極力避けようと手を尽くしており、当人に苦痛ではなく幸福をもたらす持続可能な食生活を編み出そうとしているのだ。
僕自身はちょうど体重と健康の目標を達成してしまったから、これ以上健康のために努力を続けようという動機が薄れてしまっているところだった。現在の体重の「維持」は、目標体重に到達しようとするのに比べればずっとつまらない目標だ。そんなときに「Spectrum」を読んだことは、いかに自分の健康を維持するかについて考えを巡らせる助けとなった。そして静養ウィークエンドに参加したおかげで、すっかり気持ちも若返り、気力もまた充実し、今ではダイエットにヨガを取り入れ、瞑想もまた始めてみようかと意気込んでいる。またコンサルテーションを受けて、僕の場合、体重を維持するにはエアロビクス運動やカロリー管理に固執するよりも、筋肉量を増やす/取り戻すことで代謝量を高めた方がよさそうだということがわかった。(当初減量した20キロのうち7キロもリバウンドしてしまっていて、実はどうすべきか模索していた。)
静養ウィークエンドを企画してくれたDean以下、チームの全員にお礼を言いたい。そして思いを互いに分かち合った他の参加者の皆さんにも感謝したい。
![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)