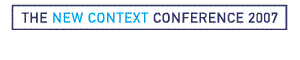Gerfried Stocker
気温が7℃で雨続きだったことを除けば、今年のArs Electronicaはとても楽しかった。今週は、5つの会議と10件のメディアインタビューがあって大変だったけど、SandraとElizabeth、それにFumiのおかげですべてうまくいき、どうにか切り抜けることができた。残念ながら、全部のインスタレーションを見て回る時間も、話をしたかったいろんなアーティストとそうする時間もなかったけれど、十分すぎるほど面白い話ができたので、今回はとても良かった。
今年は、MOGAというユニット(稲蔭教授の研究室、FumiがメインのJoi's lab、中野裕之氏のPeacedelicチームのコラボユニット)と一緒にArs Electronicaへ行った。 MOGAは、Linzに『Jump』というインスタレーションを立ち上げていた。 また、稲蔭研の勝本雄一朗氏が雨刀(あまがたな)を紹介していた。 Ars Electronicaのコンテクストでは、今まで一緒にやってきた学生達と会えて楽しかった。
ほとんどの会議の内容がオンラインのどこかで公開されることになるんだろうと思うけど、それがどこかなのかよく知らない。;-) 以前、あるビデオインタビューをArtivi.comで見たことがあるけどね。
Ars Electronicaの今年のテーマはプライバシーだ。
僕が最初に参加したセッションは、Austrian Associationとその審査員、それにArs Electronicaコミュニティーのメンバーによるセッションだった。 そこで僕は、まずジェネレーションギャップについてざっくりと話をし、それから、インターネットの新規ユーザ間で、その技術のもたらす影響や技術の使われ方がいかに違うか、また、新しいメディアを若い世代がどのように利用するかを年配の世代が理解することがいかに難しく、しかしまたいかに重要かについて話した。僕は、何人かの審査員との対談で、彼らがとても前向きであることに非常に感銘を受けた。僕はまた、将来の地球規模での民主化にはGlobal Voiceが重要であることも話した。僕は、政治家たちよりも連邦判事たちのほうが、民主主義やプライバシーの犠牲といったことについて、もっと長期的な視点で考えられるんじゃないかと思っている。 アメリカの10th Circuit Courtによる最近の判決が示すように、すぐれた判事がいることは素晴らしいことだ。

Summer Watson
次に参加したセッションは、将来のトレンドに関する、企業の役員達とのディスカッションだ。興味深いプレゼンがたくさん行われた良いセッションだった。僕が一番面白いと思ったのは、イギリスのソプラノオペラ歌手、Summer Watsonによるプレゼンだった。彼女は、北極点へのlast degree(北緯89度から90度まで)をスキーで滑り、環境問題への行動を呼びかける目的で、北極点でアリアを歌うと宣言した。
僕はこの後、彼女と一緒にコーヒーを飲み、Creative CommonsやオンラインIDについてたくさん話をした。そして、僕は Summer WatsonのWikipedia記事を書こうと思い立った。
僕はまた、WoW(World of Warcraft)のセッションも行った。これについては詳しく説明するまでもないよね。

Volker Grassmuck
それから、Leonard Dobuschとセッションを行い、Free NetworkやFree Knowledgeの重要性について話をした。 重ねて言うけど、僕は、このブログを読んでいる皆さんが、僕のポジションがどういうものであったか想像できると確信している。LeonardはLinz市長の息子でもあるんだけど、彼は、公共アクセスのサポートに関して市政が果たすべき役割について面白い考えを持っている。彼は最近、ある本を共同編集で出版したんだけど、その本では、公共アクセスに関する様々な議論が行われているんだ。彼はVolker Grassmuckの論文を引用したのだけど、Volkerはその論文の中で、コンテンツを提供する公共スペースをWeb上に設けることが重要であると主張しているんだ。
最後に僕は、パネリストとして授賞式とFair Musicの発足会に参加した。 Fair Musicの背景となったアイデアは、音楽にもFair Trade markに相当する何かを作ろうというものだったんだ。Fair Trade markが、Fair Tradeの要求基準を満たしている製品を特定しようとするものであるのに対し、Fair Music markは、アーティストや消費者を公正に扱っている企業やプロジェクトに与えられたものなんだ。ここで言う「公正」とは、報酬を公正に配分してもらっているアーティストのことや、音楽ビジネスの「Northern dominance」への偏向に抵抗して多様性を促進するプロジェクトなど、いろいろなことを意味している。
Fair Musicに関して、僕は、新しいビジネスモデルの必要性や、Creative Commonsの果たす役割を中心に話をしてきた。
Ars Electronicaで僕が撮影した写真をFlickrにアップしておく。
![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)